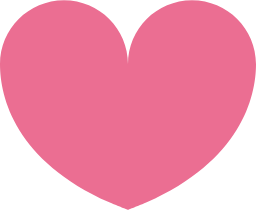


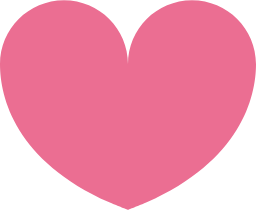


前回(『近未来の医療者像【前編】―医療者の能力として重要でなくなること』)では、ごく近い将来に、専門サービスを必要とする当事者が、専門情報に直接アクセスすることができる環境について記述しました。その上で、今まで「専門的な知識をよく知っていること」「知識を分析し、最適解をクライアントに提示できること」によって自らを成立させ、クライアントからの信頼を得ていた専門家が行っていたことの多くについて、クライアント当事者と情報技術との間で直接やり取りが行われるようになることで、専門家を専門家たらしめる能力に大きな変化がおとずれるであろうということについて言及しました。最終回である今回は、IoT/AIが社会実装された時代における専門家のすがたと役割について、特に医師をイメージしながら考察したいと思います。
ここ数年、がん診療連携拠点病院を中心に、「がんゲノム外来」という外来が自由診療枠で運営されるようになってきました。今は「がんゲノム外来」という名前になっていますが、ゆくゆくは「がん」の枕詞は外され「ゲノム外来」に変わっていくでしょう。ゲノム外来で行われることや、その現場で立ち現れるジレンマは、おそらく将来の医療者像を見通していくうえで重要な示唆を与えてくれるかもしれません。
ゲノム情報というのは実に複雑に見えますが、私はむしろ、きわめて単純な情報だと解釈しています。なぜなら、ゲノム情報は人間の一生を通じて変わることがないという特徴、もう一つは、血液検査のようなごく単純な検査によってその全体像を知ることができてしまうという特徴を持っているからです。ゲノム情報の全体を知る上では、たいそうなセンシング技術は必要なく、IoTのような継続的なデータ収集技術も必要ありません。
また、もはや個人の全ゲノムシークエンス解析は10万円以下でできるほど価格が下がっており、これからもどんどん安くなっていくでしょう。すなわち、ゲノム情報に基づいた個人の健康リスク評価とその伝達は、現時点ですでに当事者と情報技術との直接のやり取りで完結する環境にあります。ゲノム解析において、遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(HBOC)の関連遺伝子が発見されることはしばしばあります。そして、はじめてHBOCリスクについて知ってしまった女性はもちろん激しい不安にさいなまれます。遺伝子関連の健康リスク情報は当事者以外にも、姉妹や子供などにも当然影響し、その中で「知らせてほしかった」「知りたくなかった」などのプライバシー情報に関する倫理的な問題がしばしば発生します。さらに難しいのは、HBOCのように有名な遺伝子疾患以外に、例えば「Aという遺伝子とBという遺伝子とCという遺伝子がそろうとXという病気に1.15倍かかりやすくなる」というような、むちゃくちゃ微妙な情報が無限に生まれてくるであろうことが分かっています。その時、その事実を伝えるだけならそれは何の難しさもないでしょう。ただ、遺伝子解析を実行しあいまいで膨大な健康リスク情報を知ってしまった多くの当事者にとって、それは予期せぬ災難です。「知りたくて知ったのだから、あとは自分で解釈し身の振り方を決めましょうね」というわけにはいかないと、私は思います。
遺伝子情報の解析からはじき出される個別化された健康リスクの結果に対して、その結果を解釈し、意味を与える専門家の役割が必要になることが示唆されています。そして、遺伝子検査そのものが安価に行われるようになればなるほどその需要は増え、今後はそれらのサービスに対応するために遺伝子産業はまた高額なコストを生んでいくであろうことが懸念されています。
ゲノム外来で立ち現れるような問題に対して医療専門職がかかわっていくべき事柄はとてもたくさんあるのですが、最初に示した通りゲノム外来で医療者に求められる新たな役割や期待は、最もシンプルな設定であるといってもよいかもしれません。
情報技術に当事者が直接アクセスできる環境で、当事者が自分に関する情報を継続的にセンシングとIoTを通してアップロードするような環境を想定した場合、個人の健康情報に関する分析は極めて複雑なものになるでしょう。WEBカメラやネット冷蔵庫などによってセンシングされる生活情報は、遺伝子のように生涯変わらないものではなく日々更新されるものです。そして、分析されるデータの中には、例えば椅子から立ち上がるときの体重移動変化など、“コトバ”として定義することができないようなデータも多数含まれるようになるでしょう。
そうなると、AIによって分析され提示される個人の健康リスクについて、「なぜあなたがこのようなリスクを持っているのか?」ということを説明することは専門家にとってもほぼ不可能になると私は予想します。それはもはや純粋な「医学的解釈」のレベルではなく「文脈理解を踏まえての解釈」のレベルとなっていくでしょう。同時に、情報技術が当事者に提供するのもまた「あなたの診断とその確からしさ」や「あなたが将来の特定の健康イベントに遭遇する確からしさ」の結果であって、どのような経緯でその結果が生み出されたかについて、当事者が知りたいと感じているような返答はできないと思います。極端に言うのなら、すべては「ビッグデータを詳細に解析した結果このような答えが出た」という一言に集約されてしまうことなのかもしれません。結果としての事実を知った患者は、「理解」のレベルでその事実を受け入れることはできるかもしれませんが、「認識」あるいは「腑に落ちる」というレベルでそれを受け入れることはとても難しいことのように私は思います。
「患者―医療者関係」という二者関係が「患者―情報技術―医療者関係」という三者関係に変容する中で、情報技術は“正確なあいまいさ”を持つ情報(例えば、10年以内の心筋梗塞発生リスクは3.7%±2.2%である、などの情報)を当事者に提示するとともに、当事者が持つ文脈や価値観とは別の次元で「あなたは次に何をするべきか」についてのやはり“正確なあいまいさ”を持つ推奨(例えば、「10段階のうち3の強さで手術をすることを推奨する」など)を当事者に提示するようになる時代がやってくるでしょう。この時に、専門家(医療者)は当事者(患者)と情報技術との間でその二者を取り持つような存在を期待されると私は考えています。コンピューターが情報のインプット/アウトプットの矢面に立つ「情報端末」なのだとすれば、出力された情報に文脈や意味を持たせること、あるいは、患者の不安や期待をくみ取ったうえで情報技術にデータを加えていくこと。いわばある専門サービスに関する情報をやり取りする上での「感情端末」としての役割を専門家は期待されていくでしょう。
いくつもの専門家の中で、特に医療専門職は情報が生み出す不安や、当事者が決断を行ううえでの覚悟などに直接触れる代表的な専門家です。第8回『ポスト安心希求社会での個人と社会のあり方【中編】―「知る」ことと「自己変容」との関係』で取り上げた、知ってしまうことで発動する「知恵の実システム」と、それによって得られる「意味づけとともに知る」ということ、さらには、知ったうえで正しく不安になり、正しく葛藤すること。これらの助けとなるのが、専門的な視座からの知恵を持ち、専門家としての文脈と価値を持つ集団としてのプロフェッショナルなのだと私は考えます。
「感情端末」としての専門家は、情報技術からテキストをアウトプットされ「知ってしまった」当事者の決断に対して専門家の視座で解釈を行い、情報が提示してくる正確なあいまいさを持つ推奨に覚悟を与えていく役割を持つかもしれません。さらには、決断後に立ち現れる新たな物語に対して、当事者が情報とどのように付き合っていけばよいのかに対して指南を行っていく役割を与えられるでしょう。
当事者と情報をつなぐ「感情端末」としての役割に専門家の役割が移行していくとともに、専門家が獲得するべき能力も変化します。その中には、もともと必要とされていた能力であり、さらに高いレベルでの獲得が必要な能力とともに、今までは必要でなかった、あるいは、むしろ持っていることが不徳とされるような能力が、むしろ専門家の要件として重要なものになってくることも想定されるかもしれません。例えば、以下のような能力は近未来の専門家像の中で、むしろ重要な職能になってくるかもしれません。
以上のようなことが、果たして近未来の医学校で医学生に教えられるのだろうかと言うことについてははなはだ自信がありません。ただ、確かに主張できることは「記憶力と分析力に優れ、迅速に情報を集め、最速で唯一の最適解を導き出す」という、これまで「優秀な医師」をイメージさせる能力とは大きく異なる医師像・医療者像を医師やその他の医療専門職は描きなおす必要がある、ということです。
今回、1年以上にわたってAI/IoT社会における健康のすがた、病気の意味、からだとこころの関係、そして、近未来の医療者の役割などについての連載を続けさせていただきました。この連載を通じて私自身も多くのことを学びましたが、本連載のコンセプトについてもう一度ここで振り返るなら、それは、機械の故障を修復したり部品交換をしたりするように病気とケアを位置づけてきたヘルスケアのパラダイムとは異なるパラダイムのヘルスケアが今後とても大切なものになってくるであろうということです。その「新しいパラダイムのヘルスケア」のキーコンセプトを端的に言うのなら「うまくいかないからだとこころを適当にやりくりしていくヘルスケア」なのだと私は改めて主張します。このパラダイムのヘルスケアには、ケアのゴールが設定されないことがしばしばあるでしょう。そして、そもそも問題解決を目指さないということもしばしばあるでしょう。「セルフケア」の意味は「自己管理」ではなく「うまくいかない自分のからだとこころを愛でる」ことに変わっていくかもしれません。中心は患者でも専門家でもなく、「病い体験」そのものが中心となるようなケアを私たちは当然のものとして考えるようになるかもしれません。こんなウキウキするこれからのヘルスケアのかたちの変容に、少しでもかかわることができれば幸せです。
(イラスト:おおえさき)