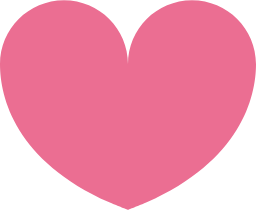


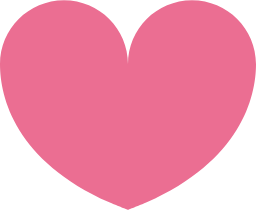

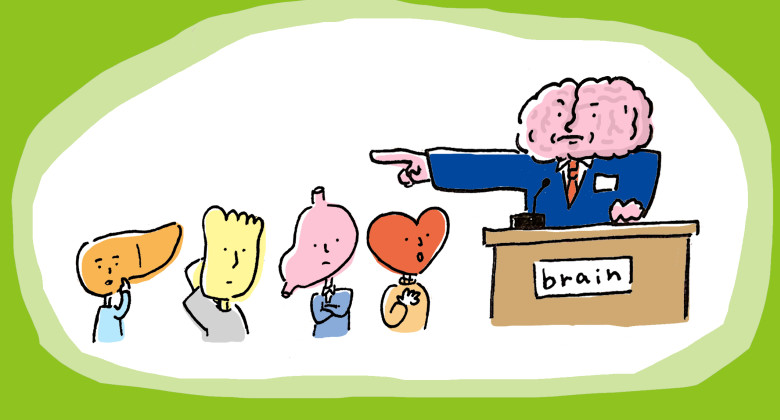
前稿(『AI/IoT時代のセルフケア【前編】―因果モデルと原因制御の方法論を超えていく』)では、からだの様々な不調に対して今まで医療が行ってきた因果モデルに基づく問題解決アプローチ、その方法論として“制御・抑制・削除”によって問題解決を図っていくことが限界にきていることについて、そして、そのアプローチを超えていくヒントとなるのが「いろいろ」と「たまたま」に思いをはせていくことであるということについて論考を行いました。また、「古いアプローチ」として「脳による身体の支配」について指摘をしました。本稿ではこの「脳による身体の支配」の解説から始め、その関係性を再構築して生まれる新しいセルフケアのコンセプトについて考察したいと思います。
「脳が身体を支配していることでからだは成り立っている」という前提認識は、合理性が高いように見えます。実際に、解剖上は自律神経などの特殊な場合を除き脳が身体のあちこちに信号を送るとともに、信号を脳に集約させていく仕組みとなっています。さらに、いわゆる「意識」も脳の中に存在しているため、あたかも人間のからだは脳の持つ意図に絶対的に服従して動くシステムであるかのように見えます。
すべてをつかさどっている中枢が存在し、からだの一つ一つのパーツはその中枢に従うという一方向性の命令システムを前提として、からだのしくみは説明されてきました。そして、私たち医療の専門家は今でも大方その前提の中で、からだに何が起こっているのかについて理解しようとしています。
数年ほど前から、私はこの前提に疑問を感じるようになってきました。中枢である脳からからだの全てに対して指令が出され、すべての感覚が脳にとって都合の良いように情報として集約されるという論理は、まるで中央集権社会のようです。
中央集権的な社会は、社会全体を統治するという目的を都合よく達成するためのしくみとしてわかりやすいですが、世界の情勢を見るにつけ、社会のすべての情報が中枢に集約され、中枢からすべての指令が下されるというような社会はうまくいかないし、その社会に住んでいる人たちを幸せにしないと私は考えます。まさに、近未来小説に登場するディストピア社会では、このような中央集権的な社会が価値を一色に染め上げ、人々の思考を停止させるような状況が描かれています。昨今の臨床場面においてなかなか解決が難しい健康問題は、このような既存のパラダイムにおいて説明されていた脳(中枢)と身体(部分)との統治関係で健康を説明することが困難になってきていることを表す現象なのではないかというのが私の最近の仮説です。
先ほど「自律神経などの特殊な場合を除き脳が身体のあちこちに信号を送る・・」と書きましたが、人間のからだには自律神経システムが存在します。腸や心臓、あるいは呼吸は、程度の差はあれ脳の指令に絶対に服従しているわけではないのです。さらには人には「感覚器」というものが存在しています。目や耳はその代表的なもので、感覚器を解剖していくと、そこに実に複雑なセンシングシステムがあることがわかります。からだのバランスがうまくないとき、感覚器は脳にとって都合のいい感覚をキャッチせず、さらにその感覚の伝え方も脳にとって都合の悪い伝え方をしているのかもしれません。
そう考えると、過敏性腸症候群やめまい症、慢性疼痛、耳鳴、前兆を伴う片頭痛、気管支喘息などの「身体の表現」は、自律神経や自律神経に関連する身体臓器、あるいは感覚器と脳との間に何らかのコミュニケーションの軋轢が生じている状態として理解することができるように思います。身体は、脳の一元的支配を望んでいません。同時に、脳も常に自分がからだの中枢として統治を期待されることを望んでいないのではないかと思います。なぜなら、現代の社会は今までよりももっと複雑になってきているし、そのような社会の中で、脳だけがからだのコントロール機能を一手に引き受けることに無理が出てきているからです。そして、身体が脳の無理やりなコントロールから自らを解放していく所作、あるいは、脳にとって都合がよい信号だけを身体が受け取らず、主体的な感覚を身体が脳に伝えることによって、それを脳が受け止めきることができないような状況が、現代医療で説明のつかない体の不調として表現されているのだというのが今の私の仮説です。
さらには、おそらくこのようなからだの関係性は、手足や臓器、感覚器に限ったことではありません。例えば、免疫システムなども立派なからだの一部です。再発性の蕁麻疹や気管支喘息が、全体的な体調やからだと環境との不一致によっておこるという説明はなんとなく説得力があります。そして、これらは一部のアレルギー疾患に限ったことではなく、リウマチのような病気にも一部当てはまるような気がします。
このように見ていくと、「器質的疾患かそうでないか?」という分類もパラダイムとしては古くなっていくのではないかと私は考えています。すべての身体の不具合は関係性の中に存在していて、その中で近代-現代医学が因果モデルを用いてロジカルに説明できる部分だけを現代医学の文法として「器質的疾患」と呼んでいるだけかもしれません。
慢性疼痛、過敏性腸症候群、慢性蕁麻疹や繰り返すめまい症などの「からだの困りごと」に対して現代の医療が行っているアプローチは“制御・抑制・削除”の原則に基づいたものです。そして、そのアプローチは基本的にうまくいっていません。一つ一つをつぶしにかかっても、モグラたたきのように不具合は別の表現型として立ち現れます。“制御・抑制・削除”のアプローチは、脳の一元支配のアプローチそのものです。そしてそのような方法論でからだの不具合に対して問題解決を試みる既存のパラダイムだけでは、現代の複雑な健康問題をうまく取り扱うことができないのだと思います。
では、新しいパラダイムでのヘルスケアは、からだと脳との関係をどのようにリモデリングすればよいのでしょうか?一言で言うなら、それは、からだ全体が脳に対して「脳もまたからだの仲間の一つ」と捉えるようなケアの形を作っていくことだと私は考えています。
「脳もまたからだの仲間の一つ」というイメージとケアを結びつけることはちょっと困難かもしれませんが、私はここ数年明らかにこのスタイルを自分の臨床の一部に取り入れています。臨床応用としてもっともイメージしやすいのが、最近注目されている「マインドフルネス」です。
マインドフルネスに対しては、禅から宗教臭さを抜いて欧米っぽいスキルベースの方法論に調理し直した、というような理解がされていますが、私も似たような理解をしています。マインドフルな状態とは、すなわち脳が体を統治している状況をやめてからだの一部に溶け込んでいる状態のことを指している、というのが私の理解です。例えば、禅寺でお坊さんたちが一生懸命床の拭き掃除をするのはマインドフルな状態を作るための所作です。床掃除という、からだを使って環境を変化させていくような動きをからだが行っている時、脳もまたからだの動きとともに床の上を雑巾が滑っていく風景に調和しているのです。
慢性疼痛やめまいなどの症状を持つ患者さんに対して、しばしばマインドフルネスが処方されそれが有効であるのは、脳が身体制御に対する過剰となった責任感のために生じている軋轢のようなものをリセットするようなことをマインドフルネスという所作が助けているからなのかもしれません。私の臨床では――私自身の修行が足りないからかもしれませんがーー瞑想という所作でマインドフルな状態に持っていくことがあまり得意ではありません。その代わりに、からだのあちこちを動かすエクセサイズを行う際に、脳をその動きに連動させるイメージを持ってもらうようなアドバイスをしています。
例えば「ラジオ体操毎日してみましょう。その時に、いろいろなことを考えながら体操するのではなく、ただただ体操しましょう。あと、『体操で腰の筋肉をほぐす。それによって腰痛改善』みたいなことを考えずに、ただただ『ぐるんぐるん』みたいなことだけ考えてください」というようなお話をしています。このような所作を毎日少しの時間だけでも取り入れていくことで、からだという社会において常に脳が統治機能の役割と責任を持ち続けるような状況から、からだ全体でからだをメンテナンスしていくようなしくみに変化させていくことで、臨床上は確かに状況が改善することが多い実感があります。私はこれを「からだの民主化」と呼んでいます。
臨床においてもう一つ大切にしている実践イメージは、「民主的なからだ」を作っていく過程において、なるべく「制御」の論理を持ち込まないようにするということだと私は考えます。例えば、新たな症状が出てきた時にその症状の発現を「本来現れるべきではない想定外の厄介なノイズ」として、削除の対象とするのではなく、新たな症状がそこで立ち現れた意味について考えてみる、というやり方をしていく、ということです。
からだが民主的な存在であれば、何か一つの反乱事象が制圧されたとき、その制圧が引き金になって次の反乱事象が起きることは合点がいきます。薬、あるいはその他の医療技術によって制圧されたある健康上の不具合事象は、民主的なからだに向かう何らかの必然的なプロセスである可能性があります。その視座は、主流となっている“制御・抑制・削除”の方法論を主体とする現代医学があまり持ち合わせていない(全くないわけではありません)部分です。これからのヘルスケアは、ある不具合事象を目にしたとき「からだという社会においてここで起こっている不具合にどのような意味が存在するのか」ということについて思いをはせることについて、重みをつけていくべきだと言うのが私の意見です。
そして、あえて個体のからだに何の不具合もないことをもって「健康」とし(まさにこれがWHOのかつての健康の定義なのです)、その定義上の健康に固執するべく“制御・抑制・削除”を繰り返していく、というやりかたから、もう少し「ゆるい」やり方にヘルスケアのかたちを変容させていくことが大切なのではないかと私は考えます。そのコンセプトを端的に表現するなら、「“やりくり”のヘルスケア」なのだと思います。
“やりくり”するとはどういうことでしょうか?一つは、自分が常に不完全な存在であり、流動する存在であるということを認めることだと思います。例えば、財布の中にあるお金はつねに流動的です。そして、常に十分ではありません。常に十分ではないという前提と、そのなかでも常にちょっと潤沢だったりかなり厳しかったりする時期が繰り返されるという前提を持ったうえで、それでも幸せに暮らす工夫を日々し続けることが“やりくり”なのだと思います。
さらには、そこにある問題を「あるべきではないもの」「解決されるべきもの」としてみなすのではなく、問題を抱えたままよりよい状況を求め続けることが“やりくり”の重要な特性です。これは、よく臨床医(私も)が言う「病気とうまく付き合っていきましょう」という言葉が持つ意味とは若干意味が異なっていると私は認識しています。医師が「病気とうまく付き合っていきましょう」という時、「解決できない問題は受け入れるしかない」というニュアンスが少なからず込められています。健康の“やりくり”は、むしろ現状を受け入れ難いものとしてとらえることから始まるのかもしれません。今自分のある資源を大切にしながら、しばしば人から援助をもらい、苦難を伴う不具合に意味を感じながら自分をメンテナンスしていくことが“やりくり”のコンセプトなのだと思います。
“やりくり”のヘルスケアにおいては、薬や手術も、制御や削除の手段ではなく自らの健康をうまくやりくりしていくための工夫の一つとして位置づけられます。近未来の情報時代を生きる中で、解明できない複雑なものを複雑なままとらえ、全体を全体として取り扱うスキルが健康生活においても必要になってきます。その中核的なコンセプトして“やりくり”は大切なものになってくると私は考えます。不安も、苦痛も、障害も、ふり幅のある余命も、からだごとうまくやりくりしていくための方法について、今後さらに言語化していくことができればと考えています。
最後に、このようなパラダイムシフト的な視座を実践メソッドして外挿する際に気をつけなければならないのは、単に既存の価値観に対する抵抗勢力としてコンセプトを位置づけないということです。それは歴史の焼き直しになってしまいます。たとえば、前回「因果モデルを超える」とか言いながら、今回「身体がおかしくなるのは脳と身体の仲が悪いから」みたいな言説は、これもまさに因果じゃん、というツッコミは当然あるかと思います。
前稿と本稿で私が提示したヘルスケアの形は、今までの因果モデルに基づいた問題解決アプローチを否定するものではなく、補完するものとして外挿されるのがよいのかと個人的には思っています。ただ、ヘルスケアだけではなくすべての領域において、部分を切り取り緻密かつ分析的にアプローチするという方法論は、おそらく人間よりもコンピューターの方が能力としてはるかに優れています。その部分をコンピューターに代行してもらうと決めた時、私たち人間社会はより深淵で複雑な私たちの不具合に向き合うようにできているのかもしれません。「いろいろ」と「たまたま」そして“やりくり”のヘルスケアのコンセプトは、私たちがより重みづけをもって向き合う具合の悪さへのアプローチの一つとして装備しておいてもよいかもしれません。